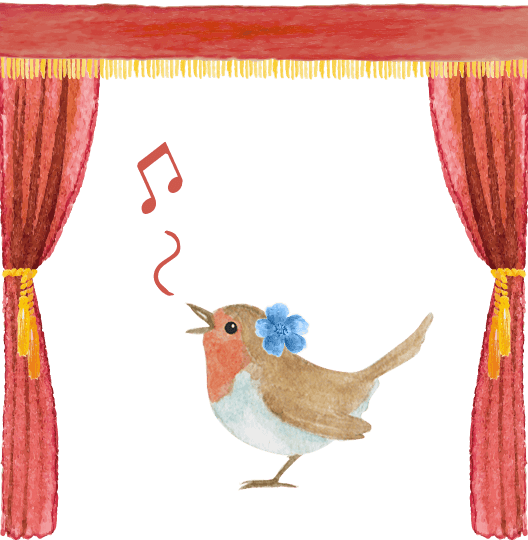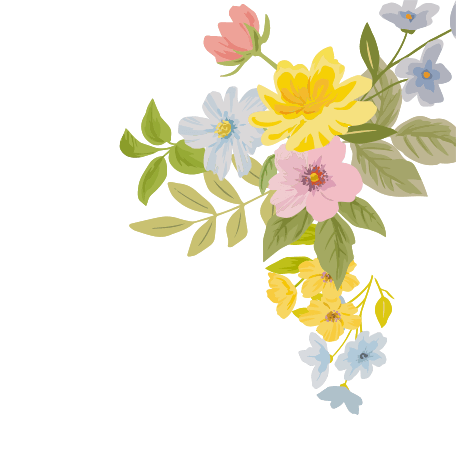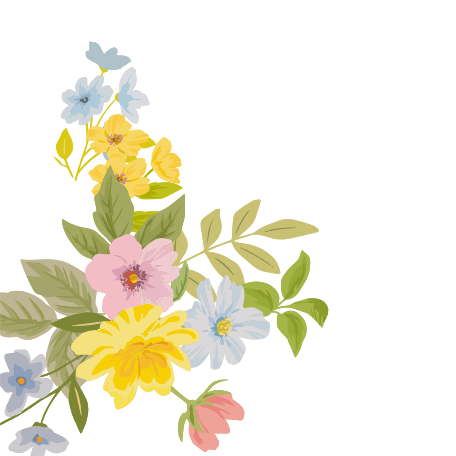抒情美と劇的迫真性 作品の真価が引き出された上演

1863年9月30日、パリのリリック劇場で初演された《真珠採り》。ジョルジュ・ビゼーが《カルメン》の12年ほど前、24歳で作曲したこのオペラは、大胆な和声に支えられたエキゾチックな抒情性があふれている。初演は熱狂的に迎えられながら批評家には酷評されたが、近年は作品の美しさが再評価され、世界的に上演される機会が増えている。
しかし、日本では2005年にヴェネツィアのフェニーチェ劇場の引っ越し公演を最後に、上演された記憶がない。それだけに、2022年3月19日、フィオーレ・オペラ協会が浅草公会堂で上演したことには価値があった。
舞台はセイロン島。部族の長になったズルガと漁師のナディールが、かつて同じレイラを恋した思い出を語る。そこにヴェールをかけた女性が高僧ヌーラバットに伴われて現れる。巫女になったレイラだった。ナディールはレイラに心を打ち明けるが、ヌーラバットに捕まってしまう。ズルガはナディールを助けようとするが、密会相手がレイラだったと知ると、嫉妬して2人に死刑を言い渡す。しかし、ズルガは後悔して2人を逃がすが、ヌーラバットに裏切りを告発されて殺される。
弦と木管、打楽器、ハープ、ピアノからなる小編成のオーケストラはステージの右手に置かれ、仲田淳也の指揮で短い前奏曲からこのオペラに特有のエキゾチシズムを引き出した。舞台には海辺の映像が流れ、合唱する漁師たちの民族的な衣装が美しい。簡素ではあるが、場面に引き入れられてしまう。照明などで状況の変化をさらに表現する余地はあったが、下手に凝って興を削ぐより好ましい。
ズルガは須藤慎吾(バリトン)。いつもながらの流麗な歌唱で、フレージングが洗練され、フランス語も美しい。敵役がこうしてスタイリッシュに歌われると舞台が締まる。そこに現れた又吉秀樹(テノール)扮するナディールは、力に頼らずニュアンスを活かした歌唱で、抒情性をうまく引き出している。
だから、フルートとハープに伴われたナディールとズルガの二重唱も、又吉がソットヴォーチェで情感豊かに歌い出すと、2声が重なり高音の美も相まって、美しい旋律に生命が宿った。そこに西正子(ソプラノ)のレイラが、神秘的な表現で自らの登場を印象づけた。ヌーラバットの杉尾真吾(バス)の品位ある重低音が、ドラマの背景にある宗教を強く印象づける。これら主役4人の歴史的衣裳も舞台に色を添える。
レイラを思い続けてきたことを告白するナディールのロマンス。胸声と頭声の間を巧みに行き来しながら優美に歌われた。このため、続くレイラの装飾に彩られた祈りを、ナディールの思いと重ねて聴くことができた。西は音域によって音色が変わりがちではあるが、なにより歌唱に華がある。
第2幕は背景に満天の星。舞台はヌーラバットの端正な低声で引き締められ、レイラの心の揺れが客席に伝達する。ナディールとレイラの二重唱も甘い抒情に切々たる思いが重なって心に迫り、その後は息つく間もない迫力だった。須藤の悪相には凄みがあるが、それでも品位が崩れない。
第3幕の背景は火刑場だろう、星空の下に火が炊かれている。そこで切羽詰まった思いが交錯する。ズルガは友人に死刑を命じたという自身の判断を悔い、レイラはナディールの助命を切々と訴え、それを聞いたズルガに再び憎悪が呼び起こされる。歌手たちの集中力が高まり、それを雄弁なオーケストラが支えた。終幕は死刑を実行しようとするヌーラバットと止めるズルガ、断末魔のズルガと救われた2人、という対比も鮮やかだった。
力ある歌手陣と小編成でも雄弁なオーケストラ、簡素でもわかりやすい舞台が相まって、名作の真価が久しぶりに解き放たれた2時間だった。

筆者プロフィール
早稲田大学卒業。声楽作品を中心にクラシック音楽全般について原稿を執筆。声の正確な分析と解説に定評がある。著書に「イタリアを旅する会話」(三修社)、「イタリア・オペラを疑え!」(アルテスパブリッシング)。毎日新聞クラシック・ナビに「香原斗志『イタリア・オペラ名歌手カタログ』、「GQ japan」web版に「オペラは男と女の教科書だ」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、近著に「カラー版 東京で見つける江戸」(平凡社新書)。