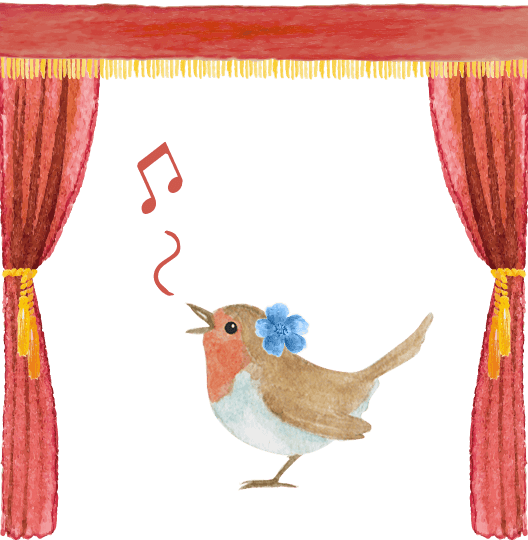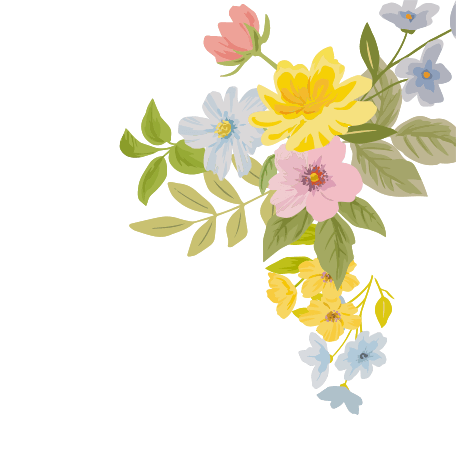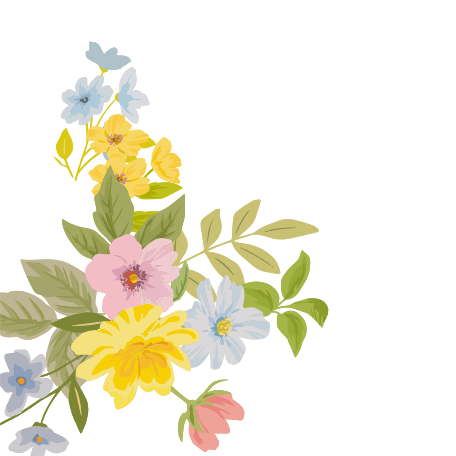多士済々によって豊かに彩られた声の饗宴

10月12日、豊洲シビックセンターホールの舞台には、日本のオペラシーンをリードする歌手たちが並んだ。価値あるオペラ公演を提供し続けるフィオーレ・オペラ協会の設立15周年を記念した「秋のコンサート~フィオーレより感謝をこめて~ Vol.2」。そのうち男声陣はみな国立音大1992年入学の同窓生だと知って、まず驚かされた。一大学の一学年に、これほど多士済々が集まっていたという事実に、である。
オペラの豊かさが色とりどりの声に支えられているとしたら、この競演はまさにその豊かさが体現され、声の色彩の饗宴となった。当日の演奏を振り返ると、歌われた曲の多彩さと相まって、その印象をいっそう強くさせられる。
1曲目はモーツァルト《コジ・ファン・トゥッテ》の三重唱。渡邊公威のやわらかいテノールに、鶴川勝也(バリトン)と斉木健詞(バス)の質が高い低声が重なる、上質なアンサンブルで幕を開け、ドニゼッティが3曲続いた。《愛の妙薬》の、ネモリーノが「妙薬」を買う金のために入隊を決心する場面は、須藤慎吾(バリトン)のスタイリッシュなベルコーレと、渡邊の真に迫るネモリーノとの駆け引きに心がなごむ。《ドン・パスクワーレ》からは、老獪さがにじむ斉木のパスクワーレと、フレージングが美しい所谷直生(テノール)の洒脱なやりとりが心地いい。続いて《ランメルモールのルチア》第1幕からルチアのアリアを、西正子が技巧を凝らして歌った。
ベルカントに酔ったあと、前半は2曲のヴェルディで締められた。《運命の力》第4幕のカルロとアルヴァーロの二重唱は、須藤と村上敏明(テノール)がヒロイックな声で激しい感情をぶつけ合いって圧巻。《マクベス》から「ああ、この父の手は」は、家族を失ったマクダフの悲哀を所谷が端正に歌い上げた。
休憩後はビゼーから。まず《真珠採り》第1幕の抒情的で美しい二重唱が、所谷のリリックな美声と斉木の品格あるバスで歌われ、《カルメン》第3幕の二重唱では、鶴川の色気あるエスカミーリョに、中村が歌うホセの豊かな声が衝突した。
そしてプッチーニ。《トゥーランドット》の「泣くなリュー」で、村上の力強いカラフに心を打たれたあとは、《ラ・ボエーム》第4幕、渡邊のロドルフォと鶴川のマルチェッロの情感のこもった二重唱にしみじみとさせられる。
さらにワーグナーまでが織り込まれているところが、このコンサートの多彩さを象徴していた。《タンホイザー》の「夕星の歌」では須藤の甘い美声に酔わされ、続いて《トリスタンとイゾルデ》の「愛と死」。一晩でルチアとイゾルデを歌い分けた西にエールを送りたい。
最後は再びヴェルディに。まず《オテッロ》第2幕の二重唱で、狡猾さを体現した須藤のイヤーゴに、怒りを募らせる中村のオテッロ。ブッファから劇的な役までを見事に歌い分ける須藤も、中村のドラマティックな表現も見事だ。《ナブッコ》の合唱「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」を全員で歌ったのち、最後は《イル・トロヴァトーレ》から、マンリーコのアリア「見よ、恐ろしい火を!」。村上の熱のこもった歌唱と輝かしく力強いハイCに、客席全体が酔いしれた。
ここまで15曲、オペラで描かれるあらゆる感情が、鮮やかに歌い分けられた15曲だった。アンコールでは、今度は中村がマンリーコのアリアでハイCを響かせるという「ハプニング」も。ちなみに、手堅く指揮をした仲田淳也も、この多士済々とは国立音大の同じ学年だったという。
オペラは声による芸術である。その豊かさが色とりどりの声によって示されるのを聴き、彼らが常連であるフィオーレ・オペラ協会による今後のオペラ公演への期待も、自ずと膨らむ。
筆者プロフィール